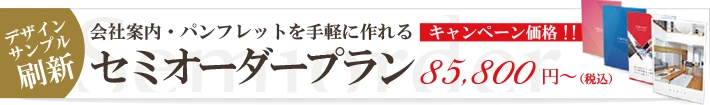- ホーム
- 会社案内制作のお役立ちコラム
- 会社案内やパンフレットで使われる用紙
会社案内やパンフレットで使われる用紙

会社案内やパンフレットを制作会社へ依頼し、デザインや内容の部分は非常に気になるところではございますが、さらに気になるのが印刷される用紙についてです。
特殊な用紙は山のようにあり、予算を掛ければキリがありませんが、まずは基本的な知識としての一般的な用紙の理解が必要です。
本コラムでは出来上がりに後悔しないためにも、見積もりでも一番分かり辛く、かつ重要なポイントでもある「紙の種類」のご説明させてもらいます。
パンフレットに使われる一般的な用紙の特色

会社案内やパンフレットなどによく使われる一般的な用紙があります。
よく使われて一般的がゆえにコストも安く抑えられ、世の中のパンフレットの9割以上がこれらの用紙を使われていると言っても過言ではありません。
そのよく使われるという用紙は下記の3つとなります。
- コート紙
- 上質紙
- マットコート紙
もちろん特殊な用紙は山のようにありますが、あくまで一般的な会社案内やパンフレットを作ると仮定した場合のお話しです。
それぞれの特徴をご紹介していきます。
コート紙
光沢のあるツルツルとした質感の用紙です。
発色が非常によいので写真やグラデーションなどが多いデザインなどに向いています。
他の2つの用紙に比べて紙の質が柔らかいせいか、同じ厚みの用紙でも若干ですが体感的に薄い印象があります。
上質紙
ザラザラとした質感の用紙です。
発色が悪いので写真やグラデーションが多いデザインには不向きです。
質感が好まれて使われる場合もあります。
マットコート紙
上記のコート紙と上質紙の中間にあたる用紙です。
発色や質感共にどちらにもバランスがよい用紙です。
弊社ではクライアントが比較的このマットコート紙を選ばれている印象があります。
と、かなり大雑把な説明ですが、だいたいはこんな感じです。
実際の質感は好みもありますし、正解は正直なところありません。

COMPANY PROFILE PRODUCTION
用紙の厚みについて

見積もりの用紙の欄に、恐らく「90K」とか「110k」とか「135K」など数字が入っているかと思います。
専門的な意味は割愛させていただきますが、この数値は紙の厚さを示す数値です。
一般的に皆さんが体感的に分かる紙厚としてコピー用紙があります。
コピー用紙は「70K」前後の厚みと言われています。
パンフレットに使用されるのは「110K」か「135K」が一般的で、弊社では「135K」をレギュラーの用紙として使用しています。
「135K」くらいの厚みがやはりしっかりした作りになる最低ラインではないでしょうか。
ちなみに見積りの表記でも1点注意が必要で、この「○○k」という表記の表現は2種類存在します。
上記でご案内したのは「四六判」という表現で、一般的な表現として使われますが、稀に「菊判」と言われる表現で見積りされている場合があります。
少々分かり辛いのですが「四六判」と「菊判」では換算が異なり、例えば下記のようになります。
- 135K(四六判)= 93.5K(菊判)
- 110K(四六判)= 76.5K(菊判)
上記はそれぞれ同じ紙の厚みですが、数字だけ見ると菊判のほうが薄く見えてしまいますね。
最近ではあまりこの「菊判」での表現は使われなくなってきていますが、昔ながらの印刷会社ですとこのような「菊判」の表現を使う事もあります。
念のため見積りの用紙の厚みの数値は事前にしっかりと確認する事をオススメします。
あとはお好みで、もっとしっかりした厚みを選ばれるお客様もいらっしゃいますが、あまりにも厚い用紙ですと中綴じや2つ折りにした場合、紙があまりの厚さにビビッてしまい、キレイに折れずに中央が若干膨らんでしまう事があります。
印刷業者によっては厚い用紙の折り加工を断られる場合もありますのでご注意ください。
紙の質感を上げる表面加工

用紙の種類もさることながら、さらに質感を上げるために表紙への表面加工もあります。
一般的によく使用されるのが「PPフィルム加工」です。
PPとはポリプロピレンの略で、書籍の表紙や名刺などにもよく使われている加工です。
紙の表面に薄いフィルムを圧着して貼り合わせる加工で、表面を保護するとともに非常に高級感が出ます。
つや消しのタイプを「マットPP」と呼びシックで上品な印象に、反対にツルツルとした光沢があるタイプを「グロスPP(クリアPP)」と呼びます。
デザインが黒ベタなどで一面が単色の場合などは触った際に手油の指紋が付いてしまいがちです。
そういった単色の色ベタのデザインの際はPPフィルム加工をされると指紋の付着などが軽減されるのでオススメです。
さらには、金箔や銀箔などを金型を使って箔を用紙に圧着させる「箔押し加工」や、凹凸状のそれぞれの型の間に紙を置き、圧を加えて絵柄を浮き上がらせる「エンボス加工」などがあります。
これらは表紙のロゴ部分などに使用すると非常にインパクトのある仕上がりになることでしょう。
用紙にどこまでこだわるのか

高級なサービスや高級な商材の取り扱い(例えば不動産業や車のディーラーなど)、または富裕層向けのサービスなどであれば、しっかりとした用紙や加工で企業やサービスの箔を見せる事は重要ですが、一般的な企業ではどこまでやるのかはハッキリと言ってしまえば自己満足です。
紙は実際の体感的な部分なので、せっかく作る会社案内やパンフレットをチープなものにしないためにも、見積もりをしっかりと確認してくださいね。